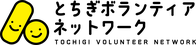●足元見られないように生きてきた
いま、福祉系大学の社会人学生(通信)をやっている主婦の宮村広美さん(仮名42歳)は、母子家庭に育った。3歳の時に親が離婚、母と妹の3人で市営住宅の長屋の暮らしだった。30数年前のパートの事務員の給料は安く、生活保護を受けていた。広美さんも小2で洗濯、小3で料理もしていた。
「母も自分も、足元見られないように暮らしていましたね」と振り返る。「長屋の子は貧乏というクラスの子の目もありました。だから足元見られないよう神経張りつめてました」。
「母から手をあげられることも多かった」と広美さん。「死ぬかと思った時もありましたよ。包丁振り回すんですから。キーキー叫び声をあげていましたね」と当時を振り返る。
●「お前は父親に似ている」憎しみは私に。
「ストレスのはけ口が、長女・中学生の私に向いていました。『お前は父親に似ている』っていう理不尽な理由なんですけど」。しかし妹は可愛がられていて、はけ口が妹に向くことはなかったという。
毎日怒られる日々、長屋から叫び声が響いた翌日は学校の中の噂になっていた。
高校は定時制だった。その後結婚し、栃木にきて10年になった。
「いまから振り返ると、母は追い込まれていたのだろう」と広美さん。「こんなはずじゃなかった、という思いが母にはあったのかもしれませんね。23の若さで子ども2人抱えて。身近に頼れる人がいないかったし。母の親戚からも私が『父に似ている』などと言われたり…」。生きていくのがキツかった、と広美さん。
「こんなに客観的に昔のことを言えるようになったのも、この2、3年ですね」。福祉の勉強をして、同じような事例を知るにつけ「なるほど」と得心したという。
母子家庭と、追い詰められた母からの“虐待”。「親の勝手な事情で」と思ったことも含めて、大人になるまで誰にも言えなかった。「勉強するまでは、過去の自分と向き合うことができなった」と広美さんは述懐する。
今の母は癌を患い、本人が少し変わった。「昔のことすまなかったね」と優しい感じになっているという。